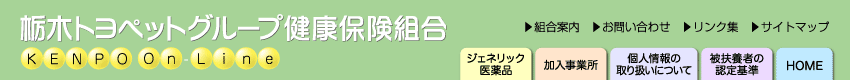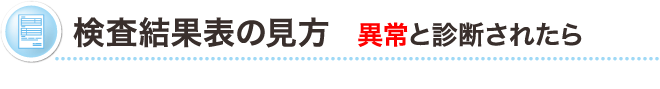 健診結果表を見たら「要再検査」・「要精密検査」とあるけれど……… 忙しいし、特に自覚症状もないからと医療機関を受診しない方は、いませんか。 去年の再検査や精密検査の結果は「異常なし」…「今年の再検査はパスしても大丈夫」と思い込んではいませんか。 身体は、年々老化し、がんや成人病になるリスクは、年を追うごとに高まります。 また、食事の影響を受けやすい血糖値・尿糖・中性脂肪などの検査もあります。正しい検査結果を得るために、健診時も含め再検査・精密検査で受診する際には、前日の夜8時までに食事を済ませ、当日は、朝食をとらずに医療機関を受診し、窓口で食事の影響を受ける検査なのかどうかを確認することも大切です。 ●尿蛋白陽性 風邪もひいていないのに尿蛋白陽性といわれたら、高血圧・糖尿病による腎臓障害や尿管結石、膀胱炎女性に多い膠原病のチェックをする必要があります。 特に溶連菌感染症の場合には、急性腎炎を発症し、慢性腎炎に移行する場合もあるので要注意です。 ●尿潜血陽性 尿は腎臓で作られ、尿管という細い管を通り、膀胱にためられて体外に放出されます。したがって、この経路のどこかで血液が混入したことになります。 考えられる異常としては、尿道炎・膀胱炎どの感染症、腎結石・尿管結石、膀胱がん・腎臓がん、膠原病・高血圧・糖尿病などの全身の病気による腎臓合併症などです。 詳しい尿と血液検査、腹部CT検査、場合によっては腎臓の組織をとる腎生検などが必要になります。 ●尿糖陽性(+) 糖は、蛋白と同様、尿に出てくることは、ほとんどありません。陽性の場合名は、糖尿病・腎性糖尿・肝疾患・甲状腺機能異常・副腎疾患が疑われます。 尿糖の検査では、採尿が食後尿か、空腹時尿かで結果が違う場合があります。食後尿である場合には、検査官にその旨を伝えましょう。 尿糖検査で陽性でも糖尿病と確定されるわけではありません。糖尿病は、さらに血糖やブドウ糖負荷試験などを行って確定されます。 ■尿でわかる身体の異常
便を肉眼で見たとき、真っ黒な便なら上部消化管(食道・胃・十二指腸など)からの出血、赤黒かったり、真っ赤であれば下部消化管(大腸・肛門など)からの出血が疑われます。 この検査は、肉眼でわからない微量な出血を検出する検査です。大腸がん検査と呼ばれていますが、陽性の場合、食道・胃・十二指腸・小腸・大腸・肛門までのどこかで出血していることが疑われます。 ●陽性 食道がん・食道潰瘍・出血性胃炎・胃潰瘍・胃がん・十二指腸潰瘍・大腸ポリープ出血性腸炎・潰瘍性大腸炎・大腸がん・痔・白血病や紫斑病など出血傾向のある病気 ●赤血球が少ない = 貧血 再生不良性貧血、痔、胃腸病による出血、子宮筋腫が疑われます。 ●赤血球が多い = 多血症 多血症では、血液の流れが悪くなり、血管が詰まりやすくなるため、心筋梗塞や脳梗塞、血栓症の原因になる場合があります。 多血症でない場合には、心臓や肺など他の病気が原因で赤血球が多くなっている場合があるので、精密検査が必要です。 ●白血球が多い 病原菌を撃退する役目がある白血球。身体のどこかに炎症があると増加します。 細菌感染症(扁桃腺・肺炎・胆のう炎・虫垂炎・髄膜炎など)、外傷、歯肉炎、歯槽膿漏、床ずれ、がん、白血病などが疑われます。 ●白血球が少ない 白血球を作る骨髄の働きが低下した場合と、古くなった白血球を壊す脾臓の働きが亢進した場合に減ります。 再生不良性貧血、悪性貧血、肝硬変、脾臓機能亢進症、放射線障害、薬剤の副作用が考えられます。 GOT(AST)・GPT(ALT)とは、肝臓・心臓・骨格筋・腎臓などの細胞に多く含まれる酵素で、これらの臓器が障害を受けて、細胞が壊れたり死んだりすると、多量に血液に流れ出てきます。 γーGTPは、腎臓・すい臓・小腸・肝臓などに多く含まれますが、肝臓が障害を受けた時だけ血液に流れ出ます。 ●GOTが高くGPTが正常 心筋梗塞・肝炎・肝硬変・筋ジストロフィー ●GOTが正常GPTが高値 肝炎・脂肪肝 ●GOT・GPT共に非常に高値 急性肝炎 ●共に高値だが、GOT>GPT 肝硬変・肝臓がん ●共に高値だが、GOT<GPT 慢性肝炎・脂肪肝 ●γーGTPが高い アルコール性肝障害・薬剤性肝障害・肝炎・肝硬変・肝がん 【脂 質】 脂質成分であるコレステロールや中性脂肪は、水に溶けません。そこで、蛋白と結合し、血液に溶けやすい形になって全身に運ばれます。コレステロールは、HDLコレステロール(血管内のコレステロールを取り除く働きをするので、善玉コレステロールとよばれています。)とLDLコレステロール(血管の壁にくっついて動脈を目詰まりさせ動脈硬化を進行させるため悪玉コレステロールとよばれています。)に分かれます。 善玉コレステロールを増やすのは、適度な運動です。また、悪玉コレステロールを増やすのは、ストレス・たばこ・肥満、減らすのは、植物油や魚の脂肪です。 一方中性脂肪は、カロリーオーバーで消費できなかった栄養分が脂肪として蓄えられている状態です。脂肪の多い食事をしていなくても甘い物(糖分)や炭水化物(ご飯・パン・麺類)の摂取が多い方は要注意です。中性脂肪で最も大きな問題は、アルコールです。深酒をした翌日などは中性脂肪値が跳ね上がります。週2日ぐらいは、禁酒を心がけましょう。 ●HDLコレステロールが低い 脳動脈硬化症・脳梗塞・狭心症・心筋梗塞・腎硬化症・糖尿病 ●LDLコレステロールが高い 高脂血症・糖尿病・動脈硬化 ●中性脂肪が高い 高脂血症・動脈硬化・脳血栓・糖尿病・肥満・ネフローゼ症候群・甲状腺機能低下症・家族性高リポ蛋白血症 ●中性脂肪が低い 慢性肝炎や肝硬変などの肝臓の病気・呼吸不良症候群 【血 糖】 血糖とは、血液中のブドウ糖のことで、生命活動を維持するためのエネルギー源として利用されます。ことに脳細胞は、ブドウ糖だけを利用して活動しています。食事によって吸収されたブドウ糖は、いったん肝臓に蓄えられ、必要の応じて血液中に放出されます。通常血液中の血糖値は、ほぼ一定の値を保っています。一定の値を保つためのホルモンが膵臓で作られるインスリンです。 朝食前の血糖値が126以上の人、又は、食事をして2時間後の血糖値が200を超えていると糖尿病と診断されます。糖尿病になって、高い血糖状態が長く続くと血管を侵され、失明・人工透析・手足の切断、そして、動脈硬化・脳血栓・心筋梗塞といった生命にかかわるような合併症を併発します。自覚症状がなくても必ず内科を受診して血糖値の管理をしてください。(症状が出たときは、手遅れで、あわてて治療しても病状は現状維持できれば良いほうで、ほとんどが悪化します。) ●血糖値が高い 糖尿病・耐糖能障害・甲状腺機能亢進症・クッシング症候群・外傷・発熱・肝硬変・膵手術後・膵炎・膵がん ●血糖値が低い インスリノーマ(膵島腫瘍)・粘液水腫・アジソン病・栄養障害・頻繁な嘔吐や下痢 【尿 酸】 人体の細胞は、毎日新しく作られていく一方で、古くなった細胞は分解され、壊されます。この時できるのが、尿酸です。ほかに、尿酸は、食べ物やアルコールを原料に作られます。ビール、モツ、肉、豆、貝などといった美味しいものに多く含まれるプリン体が原料になります。また、尿酸は、激しいスポーツやストレスによっても増えます。 尿酸は、通常尿と腸から排泄されますが、尿酸濃度が高くなって飽和状態になると足の親指のつけ根や手指の関節などにたまり痛風発作がおこります。 ●尿酸値が高い 痛風・酵素異常の病気(グルタミン代謝異常、尿酸結合血清蛋白欠損症)・尿酸生産異常の病気(白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの腫瘍) ●尿酸値が低い 家族性鄭尿酸血症・キサンチン尿症・重症肝障害 眼底検査とは、眼の奥のほうにある網膜とその血管、脈絡膜、視神経乳頭などを調べる検査です。目の病気を調べる時に行いますが、網膜は、人間の体の中で唯一直接血管の状態を観察できる部位のため、動脈硬化、脳腫瘍、高血圧、糖尿病など全身の病気、いわゆる生活習慣病の検査としても重要です。 ●正常でないとき 網膜はく離・眼底出血(高血圧・動脈硬化・糖尿病・貧血・白血病)・脳出血・視神経乳頭陥凹(緑内障)・網脈動脈閉塞症・糖尿病性網膜症・脳腫瘍・くも膜下出血・硬膜下出血・網膜黄斑変性症 心臓は全身に血液を送り出すために収縮と拡張を繰り返しています。その時血管に与える圧力が血圧です。心臓が収縮したときの血圧を最高血圧、拡張したときの血圧を最低血圧といいます。 ●最高130mmHg以上、最低血圧85mmHg以上(治療が必要) 高血圧・高血圧からくる生活習慣病(動脈硬化・脳出血・脳梗塞・狭心症など) 心臓は、血液を送り出すために拍動するとき心筋(心臓の筋肉)は、微細ま電気を発生します。その電気の強弱を波型グラフにしたのが心電図です。 脈拍が1分間に100以上(頻脈といいます。)で不整脈もある場合は、精密検査が必要です。 また、脈拍が1分間に50以下(徐脈といいます。)で、不整脈もある場合にも精密検査が必要です。場合によっては、永久ペースメーカー埋め込み術が必要となることもあります。 心房細動は、脈がばらばらになる不整脈で心房が動いていない状態をいいます。血液は、血流が遅くなると、固まる性質があるため、心房が動かないと血栓ができ、それが全身にばらまかれるといろいろな場所で血管が詰まる可能性があります。小渕前首相がこの病気でなくなりました。 陰性T波異常(05.mv以上)、ST下降(0.1mv以下)、完全左脚ブロックの場合には、狭心症や心筋梗塞が疑われますので、精密検査が必要です。 ●正常でないと疑われる病気 不整脈・狭心症・冠不全・心筋梗塞・心筋症・心肥大・心膜炎・電解質異常・薬物作用・先天性の心臓病 この検査では、呼吸器系、循環器系の病気のほか、胸部の骨格系や筋肉の様子などをみます。かつて結核に感染し、治癒した方は、肺に異常陰影があると指摘されます。結核にかかったことがないのに影がある場合には、以下の病気が疑われます。 この検査で心肥大と診断されても、若いころにスポーツをしていた方はさほど問題はありません。(スポーツ心臓といいます。)そうでない場合には、心臓病や心臓の周りに水や脂肪がたまる甲状腺の病気・肥満などが考えられますので、心臓超音波検査を含めた精密検査が必要です。 ●正常でないと疑われる病気 呼吸器系の病気
いわゆる胃のバリウム検査です。胃や腸は、筋肉を中心としたやわらかい組織でできているためX線を透過してしまいます。そこで、X線を透過しないバリウムを造影剤として使用します。また、胃の内部の正確な写真を撮るため、事前に胃を膨らませる薬を飲んだり、胃の動きを止める筋肉注射をする場合があります。 最近の人間ドックでは、胃のX線検査ではなく、内視鏡検査を選べる健診機関もありますが、内視鏡検査には、悪性度が高く進行が速いスキルス性胃がん(胃がんの10%を占めます。)の早期発見が難しいという欠点があります。内視鏡検査で、胃粘膜表面にデコボコが見えてくる段階は、かなり進行した証しです。胃壁にできるスキルス性胃がんは、胃の委縮や形状の変化を伴うことが多いため、X線検査が推奨されます。もし、食欲不振や胃のもたれ、体重減少など自覚症状がある方は、まずX線検査をなさり、異常があったら、内視鏡等の精密検査をするといった2段構えでの検査を検討しましょう。 ●検査でわかる病気 食道炎・食道潰瘍・食道がん・食道狭窄・胃炎・胃潰瘍・胃ポリープ・胃がん・幽門の狭窄及び拡張・十二指腸潰瘍・十二指腸憩室 |